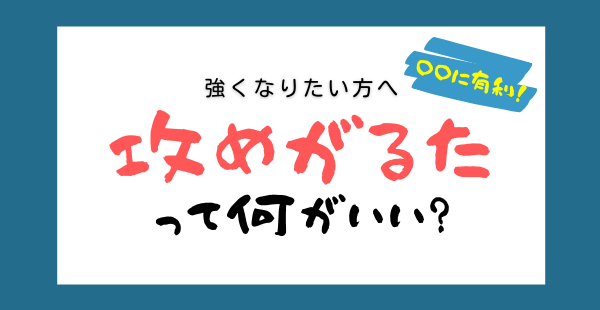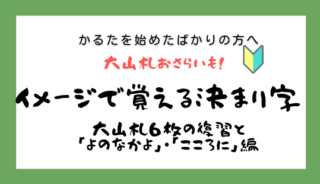どうも!Karuta Club部長の川瀬です。
競技かるたの取り方のスタイルに正解はないとされますが、その中でも最も広く普及していると言えるスタイルが「攻めがるた」です。
今回は、なぜ「攻めがるた」がスタンダードとされるのか、私なりの解釈を解説したいと思います。
競技かるたで勝つための5つの力のうち「④勝ち方を考える力」を高める参考になれば幸いです。
この記事の概要
「勝ち方を考える力を高めたい」と思った方に
- なぜ「攻めがるた」がスタンダードとされるのかわかります
- 「攻めがるた」の考え方を理解できます(理解できれば対策が考えられるようになります)
- 競技かるたの勝ち方を考える観点の参考になります
なお、本記事でいう「攻めがるた」は、相手陣を取って札を送ることを重視したスタイルとします。

川瀬名人
「自陣より相手陣をガンガン取るぜ!」というタイプですね。
"Karuta Club Room"は、第68,69,70期競技かるた現名人である川瀬将義が中心となり設立したオンラインかるた部。
競技かるたが強くなるための特典が盛りだくさんのコミュニティです。
\ 特典の一例 /