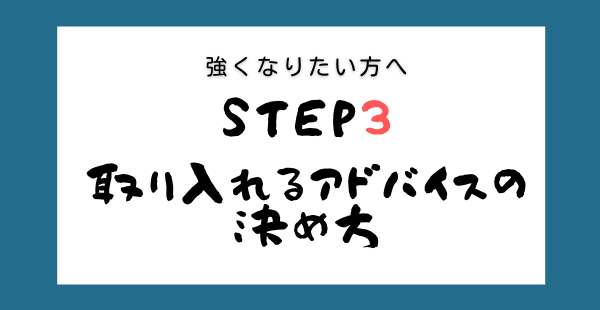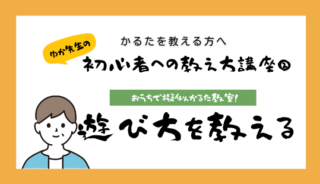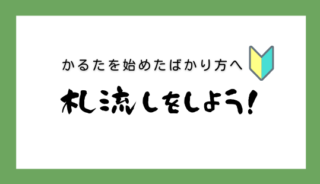どうも!Karuta Club部長の川瀬です。
今回は【かるたが強くなる】3STEP!効果的なアドバイス吸収法の最終回、STEP3についてお話しします。
強くなるためのアドバイスをたくさんもらっても、そのアドバイスを取り入れることで「本当にかるたが強くなれるのか」を見極めることができなければ、間違った方向で練習をすることになってしまいます。
結果、せっかくの努力が無駄になってしまいかねません。

どの「かるたのアドバイス」を取り入れれば強くなれるのか、私なりの分析方法を解説します。
「競技かるたが強くなりたい!」と思った方に
- 取り入れる「かるたのアドバイス」を決めるプロセスを教えます
- 取り入れる「かるたのアドバイス」の優先順位の付け方を習得できます
- 「かるたのアドバイス」の習得にかかる時間の目安がわかります
取り入れる「かるたのアドバイス」を決める5つのプロセス
以下の5つのプロセスを実践すれば、取り入れるべき「かるたのアドバイス」を見極め、かるたが強くなれるでしょう。
順番に解説していきますね。
①アドバイスはすぐに試す

アドバイスを聞いただけじゃダメなのか…
そうですね、どんなアドバイスも一度は試してみましょう。
試さないと、「アドバイスを取り入れるメリットを1つ以上見つける(プロセス②)」ことは難しいですからね。
試す際のポイントとしては、基本的にアドバイスされたら「すぐに」試すことが重要です。
可能であれば、その場で試すことをオススメします。

「鉄は熱いうちに打て」ですね!
すぐに試した方が良い理由は以下の通りです。
- 時間が経つと忘れてしまう(特に正確なニュアンスを忘れる)
- その場で試せば、試して生じる疑問をアドバイスしてくれた人に確認できる
- 試すアドバイスが溜まらない

確かに、先輩から何を言われたか思い出せないことあるな…

試して初めて出てくる疑問もありますね
そうなんです。
また、アドバイスをたくさんもらっても、同時に試せる量はせいぜい2〜3個が限度でしょうから、すぐに優先順位をつけて試しておかないと、せっかくのアドバイスが聞き流し状態になってしまいます。

聞き流しはもったいない…
もうひとつ付け加えておくと、その場で試した場合は、アドバイスをくれた人からリアルタイムでフィードバックがもらえる可能性があるんですよね。
フィードバックがあると、アドバイスを誤解してしまう懸念が払拭できます。
その場で試せなくても、別の日に確認に行くなど、できるだけフィードバックを受ける工夫をしてみると効果的です。

試しっぱなしじゃなくて、教えてくれた先輩のフィードバックを受けないと!

習慣にしたいね!
②アドバイスを取り入れるメリットを1つ以上見つける
"Karuta Club Room"は、第68,69,70期競技かるた現名人である川瀬将義が中心となり設立したオンラインかるた部。
競技かるたが強くなるための特典が盛りだくさんのコミュニティです。
\ 特典の一例 /