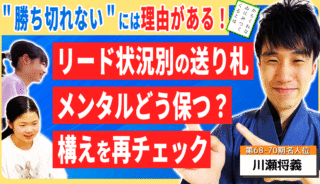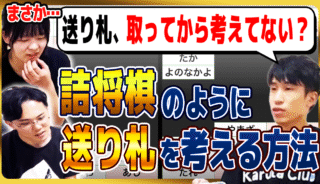どうも、千葉大会1没であんぱんを8個余らせた川瀬です。
というわけで、今回はその反省会です。
最近、反省会しかしてないな笑
タイトルの通り、大会で練習通りに取れない理由の一つの解像度が上がったので、みなさんも参考にしてみてください!
千葉大会の反省
千葉大会、結果は1回戦で2枚差で負けました。
相手は横浜隼会の橋本さんで、レーティングにも載っていないくらいのレベル感の選手のはずです。
普通にその後の2回戦も負けてましたね。
一応、言い訳をいろいろ並べておくと、
- 読みのテンポ・マイクに合わない
- 柔道畳の調整に時間がかかる
みたいな部分も多少ありましたが、一番大きいのは、前回の記事で紹介した最近練習している短期記憶を使った取り方が、大会でやってみると全然うまくいかなかったのが大きいと思います。
この取り方、「千葉大会で使うか使わないか迷う」と話していましたが、橋本選手とは1ヶ月前くらいに練習で取っていたこともあり、完全に最初から練習モードでした。
つまり、1枚目から短期記憶を使った取り方で始めました。
せめて、読みと柔道畳に慣れてからやればよかったな〜とか後で思いましたが、まあ終わった話です。
大会でうまく取れなかった理由
では、練習ではうまくいったこともあった短期記憶を使った取り方は、大会でなぜうまくいかなかったのか?
もちろん、まだ練習したてで安定性の問題もあるのですが、どうやらそれだけではなさそうで、練習と大会の違いが大きく影響していそうです。
そして、おそらく大会でうまく取れない方のうちの何割かは、ここの罠にハマっているのだと思います。
短期記憶を使った取り方をしようとすると、大会は次の札を読むまでの時間が長すぎる。
前回の記事でも引用した「西郷永世名人の世界一受けたい指導」の中で、
取り方のイメージを1つ作る時間は札で言ったら2枚分くらい

といった発言があるのですが、大会だと1枚読まれた時間でイメージを3個でも4個でも5個でも作れてしまいます。
このイメージの作りすぎがおそらく良くなくて、脳(ワーキングメモリー)の容量を圧迫し、疲労を促進させ、集中力の低下を招いていくのだと思います。
「時間が長すぎる時は暗記せずにぼーっとする」と言う人の話を聞いたことがあると思いますが、なるほど、こういう感覚かと理解しました。
暗記の配分が大会で調子よく取る鍵
整理します。
まず、暗記の回し方を2種類に分けてキッチリ区別しておくことが大切です。
- イメージを作り込む暗記
- 決まり字を高速でつぶやく暗記
前者が短期記憶を使った取り方用の暗記、後者が中期記憶を使った取り方用の暗記です。
ただ、重要なのはそこではなくて、それぞれの暗記がワーキングメモリーの容量をどれだけ使うかが重要です。
「イメージを作り込む暗記」は、かなりワーキングメモリーを使います。
つまり、頭の体力と言われるエネルギーを大きく消費しますし、他のワーキングメモリーの働きを妨げる懸念があります。
他のワーキングメモリーの働きには、音を捉えて暗記と紐付ける働きも含まれるマスので、「イメージを作り込む暗記」にコストを割きすぎると、音が聞けなくなり、反応も鈍くなります。
短期記憶には枚数制限があるという話はよくしていますが、さらに回数制限もあると思っておいた方が良さそうです。
まさに、ゲームの必殺技ゲージですね。
一方、「決まり字を高速でつぶやく暗記」では、ワーキングメモリーをほとんど使いません。
暗記の回し方が札流しの感覚になるので、ほぼ無意識の領域で行えます。
※札流しが1分を切り、30秒、40秒レベルになったら
ただ、この高速で決まり字をつぶやく作業は、札を取るための暗記の回路、体を動かす神経回路を活性化させて復習をしているだけです。
なので、あらかじめ「イメージが作り込まれている」ことが前提となっています。
これは、「イメージが作り込む暗記」で作るのはもちろんですが、普段からどれだけ取る経験を積めているかも重要です。
つまり、大会で試合の合間に暗記する時間が長い場合は、「決まり字を高速でつぶやく暗記」はやり続けてもよいけど、「イメージを作り込む暗記」は要所に絞って使わないといけないのでしょう。
大会で6試合取ることを考えると、「決まり字を高速でつぶやく暗記」だけを淡々と繰り返して、中期記憶を使った取り方メインで脳のスタミナを温存しながら戦うのはかなり合理的な戦法みたいです。
これはまさに、これまでの僕の戦い方です。
厳密には、一部「イメージを作り込む暗記」を縦分かれなどで多少使っていましたが、極力使わないようにします。
相手が速そうな札を無理して取ろうとはしないし、とにかく、すでに「イメージが出来上がって染みついた取り方」だけを淡々と繰り出していきます。
変な駆け引きをするよりも安定性も高いので、パワーで勝っていればよほど負けません。
では、短期記憶を使った取り方(イメージを作り込む暗記)を試合中にどううまく取りこめばよいのでしょうか?
ここは僕にはまだ完全には見えていないので、終盤得意な方の暗記の配分を聞いてみたいところです。
(かなり先になりそうですが、西郷さんには聞いてきます)
おそらく、1つの正解は、以下のような流れだと思います。
- 札が読まれてからすぐの時間で、一度「イメージを作り込む暗記」をする
- 下の句を読み始めるまでは、「決まり字を高速でつぶやく暗記」をする
- 下の句を読み始めたら、もう一度「イメージを作り込む暗記」をし直す
序盤は「決まり字を高速でつぶやく暗記」だけにして、中盤以降からでもよいかもしれません。
これが僕の元の取り方、中期記憶を使った取り方をベースにするとこんなところかと思います。
分からないのは、終盤型の人がどう時間を使っているかです。
「イメージを作り込む暗記」と「決まり字を高速でつぶやく暗記」の比率がちょっと違うだけなら、みんなこのバランスを調整すれば大丈夫です。
ただ、もしかすると僕が知らないだけで他の時間の使い方があるのかもしれません。
特に最終盤は「決まり字を高速でつぶやく暗記」があまり意味をなさない気もしていて、何かもう一個くらいまだ僕には見えていないピースがある気がしてなりません。
まとめ
今回は、千葉大会の反省ということで、大会で勝つための「脳のスタミナ配分術」についてお届けしました。
おそらく、僕も含めた多くの人は取らなきゃと思うあまり「イメージを作り込む暗記」をやりすぎてしまっています。
そして、ワーキングメモリーが圧迫されて、疲労も蓄積し、集中力が切れて、肝心な札を読まれた時にうまく動けない。
ただ、まったく「イメージを作り込む暗記」をやらないと、元あった場所に間違えて反応してしまったり、相手の想定通りの動きしかできずに駆け引きで不利になってしまいます。
この絶妙なバランスを見つけられると、きっとうまく取れるんでしょうね。
【追伸①】
『Karuta Club🍀』関連の有志練習会のお知らせです。
・07月28日(月)18:00-21:00 @神奈川県横浜市
・08月03日(日)9:00-12:30 @東京都文京区
・08月17日(日)9:00-12:30 @東京都文京区
・08月24日(日)9:00-12:30 @東京都文京区
・08月25日(月)9:00-21:00 @神奈川県横浜市 ※AB級のみ
・08月31日(日)9:00-12:30 @東京都文京区
夏休みということで、平日日中の練習会を他にも増やすかもしれません。
練習会は言い出しっぺがいると動き出す(いないと動き出さない)ので、積極的なリクエストがオススメです。
参加したい方は、Discord上にて参加表明をお願いします。
※上記のリンク先の閲覧には、Discordコミュニティに参加の上、案内に従ってKaruta Club Room限定チャンネルの閲覧権限の承認を受ける必要があります。
※Karuta Club Discordコミュニティの詳細・参加方法については、こちらの記事をご確認ください。
【追伸②】
次回の「Room部員限定雑談会」開催日時は8月24日(日)21:00-22:00です!
アーカイブは残しませんので、奮ってご参加ください!
ちなみに、7月は以下のようなテーマを話しました。
・高校選手権の結果
・団体戦の映像としての見せ方
・色々な人に違うアドバイスを言われる問題
・おもりをつけた素振りの是非
・団体戦の声かけの仕方
【追伸③】
- 川瀬将義に質問したい!直接感想を届けたい!
- この記事を踏まえて部員のみんなと雑談したい!
という方は、Discordの雑談部屋にコメントいただけると嬉しいです!
また、「#KarutaClub」を添えて記事の感想をSNSでコメントいただけると泣いて喜びます!
よろしくお願いいたします。